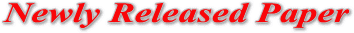 |
|
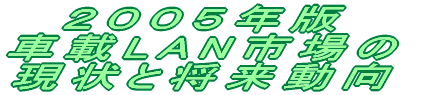 |
|
|
ご質問、サンプル頁ご希望等のお問合せは e-mail でご連絡ください。 |
|
| 購入申込書 |
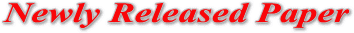 |
|
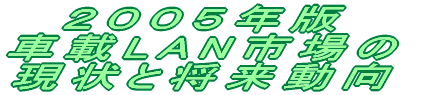 |
|
|
ご質問、サンプル頁ご希望等のお問合せは e-mail でご連絡ください。 |
|
| 購入申込書 |
|
車載LANの国際標準の波が欧州から押し寄せてきている。CANから始まり、LIN、MOSTそしてFlexRayである。独自の世界を築いていた日本市場であるが、今その波に乗ろうとしている。それは、カーエレクトロニクスを積極的に搭載し、グローバルで生産する日本車において、車載LANは必要不可欠であると認識されている為である。 CANが採用され始めた2000年以降、エコノミークラスの車にもカーエレクトロニクス搭載競争が起きた。CANのネットワークに機能を付加することによりたやすく付加価値をつけることが出来る。また量産効果によるコストダウンでさらに普及が加速するという循環になっている。 ハイエンド車の市場では世界初というカーエレクトロニクスを搭載する競争が繰り広げられるようになってきた。それにより、車に搭載されるECUの数は50個そして70個と数が増すばかりになってきた。機能が増すごとにECUを付け足すという従来のシステムは破綻をきたすのは明らかである。 そこで、新たなデータバスとしてFlexRayが登場してきた。この新しいアーキテクチャーは将来のバイワイヤーの可能性、ECU削減の可能性及びハイブリッド、FCVの高性能化を支える基盤となりそうである。 このFlexRayは欧州で作り上げられた技術である。開発は欧州で今も進められている。FlexRayコンソーシアムには日本企業が続々加入し、その数は半分になろうとしている。カーメカトロニクスで差別化しようとしている日本車において、このFlexRayを活用することは競争力を維持する上で重要である。 FlexRayに関わるソフトウエアの標準化に欧州ではAutosarが設立された。それに呼応して日本でもJasparが立ち上がった。ソフトウエアの高度化による開発負担を標準化することにより食い止めようという動きである。 このように、車載データバスとソフトウエアという開発課題に対してグローバルで解決しようという動きに対して、市場各社がどのように対応しているかを調査してみた。情報系LANのMOST、IDB-1394においても焦点を当てた。本レポートが関連市場各位のご参考になれば多大の喜びであり、且つご意見を賜ることを希望いたします。 目次 第1章、自動車メーカーのFlexRay戦略 1
1−1、自動車メーカー各社のFlexRayへのアプローチ 1
1−2、トヨタ自動車 4
1−2−1、FlexRayに関するトヨタの動向 4
1−2−2、VDIMからVDIM2そして 4
1−2−3、42Vパワーネット 6
1−3、ホンダ技研 8
1−3−1、FlexRayに関するホンダの動向 8
1−3−2、FlexRay用ハーネスについて 8
1−3−3、Steering by Wireについて 8
1−3−4、SH-AWDの次の展開 9
1−3−5、ホンダHiDSの車載LAN 11
1−4、日産自動車 12
1−4−1、CANからFlexRayへ 12
1−4−2、4Wアクティブスティヤー 12
1−4−3、インテリジェントクルーズコントロール 13
1−5、富士重工業 14
1−5−1、スバルの将来像 14
1−5−2、レガシーADA技術 14
1−6、三菱自動車 16
1−6−1、二輪、四輪インホイールモーター 16
1−7、GM 17
1−7−1、FlexRayについて 17
1−7−2、FlexRayが普及する理由 17
1−7−3、MOSTとIEEE1394について 17
1−7−4、2015年のカーエレクロトニクス概観 17
第2章、車載データバスの現状と将来動向 18
2−1、車載データバスの背景 18
2−1−1、車載データバス 18
2−1−2、欧州標準の導入 20
2−1−3、カーエレクトロニクス2015年分析 22
2−1−4、車載データバス2015年分析 24
2−1−5、CAN、LINとFlexRay 26
2−1−6、エアバッグLAN 28
2−1−7、車載OS 29
2−2、FlexRayを取り巻く環境 31
2−2−1、FlexRayの意味するところ 31
2−2−2、FlexRayロードマップ 33
2−2−3、FlexRayの残る開発テーマ 34
2−2−4、FlexRayの立ち上がり時期 34
2−2−5、FlexRayプロトコルとバージョンアップ 35
2−2−6、FlexRayメンバー 37
2−2−7、FlexRayの展望 39
2−3、Autosar 41
2−3−1、Autosarの目的 41
2−3−2、Autosarワーキングパッケージ 41
2−3−3、Autosarメンバー 42
2−3−4、Autosarソフトウエアアーキテクチャー 43
2−3−5、Autosarシステムエンジニアリング 44
2−3−6、Autosarスケジュール 46
2−4、Jaspar 47
2−4−1、Jaspar設立の意味 47
2−4−2、Jasparメンバー 49
2−4−3、Jasparワーキンググループの活動状況 50
2−4−4、JasparとFlexRay 53
2−4−5、JasparとAutosarの考え方の違い 53
第3章、FlexRay半導体の動向 55
3−1、FlexRay半導体とスタータキット 55
3−1−1、各社スタータキットの比較 55
3−1−2、FlexRay半導体ロードマップ 56
3−1−3、海外半導体メーカーの優位性 57
3−1−4、OEMのFlexRay半導体の評価 58
3−2、Freescale 59
3−2−1、FlexRay戦略 59
3−2−2、FlexRayの立ち上がり時期 59
3−2−3、FlexRay MCU 60
3−2−4、FlexRayでPhilipsと協業 62
3−2−5、FlexRayプロトコルとコンフォーマンス 62
3−2−6、品質体制について 63
3−3、Philips 64
3−3−1、FlexRay物理層チップ 64
3−3−2、FlexRayチップ戦略 65
3−3−3、Jasparでの活動 65
3−4、Bosch 66
3−4−1、FlexRay IP戦略 66
3−5、NECエレクロトニクス 67
3−5−1、FlexRay開発環境 67
3−5−2、FlexRayチップについて 68
3−5−3、BoschのIP導入について 68
3−5−4、相互接続評価について 69
3−5−5、FlexRayの必要性 69
3−5−6、Jasparでの活動 69
3−6、ルネサステクノロジー 70
3−6−1、FlexRayチップ 70
3−6−2、FlexRayスタータキット 70
3−6−3、海外半導体メーカーの動向 70
3−6−4、開発ツールについて 70
3−6−5、Jasparでの活動 70
3−7、富士通 72
3−7−1、FlexRay半導体 72
3−7−2、富士通の車載マイコン 73
3−7−3、FlexRayプロトコルスタック 73
3−7−4、スタータキットと開発ツール 74
3−7−5、Jasparでの活動 75
第4章、FlexRay開発ツールの動向 76
4−1、FlexRay開発ツール比較 76
4−2、Decomsys 78
4−2−1、FlexRay開発ツール群 78
4−2−2、開発ツール価格 80
4−2−3、dSpaceとの協業 81
4−3、dSpace 82
4−4、Vectorジャパン 84
4−4−1、FlexRay開発ツール 84
4−4−2、FlexRayツール価格 86
4−5、東陽テクニカ 87
4−5−1、IXXAT 87
4−5−2、MISRA-C 88
4−6、ETAS 89
4−6−1、OSEK v2.2 89
4−6−2、OSEKTime 90
4−6−3、Live DevicesのリアルタイムAutosarファミリー 90
4−6−4、FlexRayインターフェースモジュール「ES520」 92
4−7、TTTech/TTA 93
4−7−1、FlexRayへの経緯 93
4−7−2、TTAの特徴 93
4−7−3、TTTechの製品 94
4−7−4、FlexRay開発スケジュール 95
4−7−5、Jasparに加盟 95
4−7−6、FlexRayの実用化動向 96
4−7−7、FlexRayの日本での売り込み 97
4−8、3SOFT 98
4−8−1、BMW向けOSEK/VDX 98
4−8−2、OSEK/VDXとAutosarOS 98
4−8−3、NECマイコンへOSEKTime 98
4−8−4、Jasparへの参加 98
4−9、横河デジタルコンピュータ 99
4−10、NEC通信システム 100
4−11、ADaC 101
4−12、サニー技研 102
第5章、MOST&IDB-1394の動向 103
5−1、MOST対IDB-1394 103
5−2、MOST 105
5−3、IDB-1394 108
5−4、矢崎 111
5−4−1、MOST 111
5−4−2、PCS (Polymer Clad Silica) 111
5−4−3、ゲートウエイユニット 112
5−4−4、FlexRay 112
5−5、住友電工/住友電装 113
5−5−1、IDB-1394カメラシステム 113
5−6、豊田合成 115
5−6−1、IDB-1394光トランシーバー 115
5−7、東芝 116
5−7−1、トスリンクIEEE1394 116
5−8、NECエレクロトニクス 117
5−8−1、ワイヤーハーネスの将来展望 117
5−8−2、車載用イーサネット 117
5−8−3、並列分散技術 118
5−8−4、Ovia(Open Value interface for your Application)について 118
5−9、シャープ 119
5−9−1、MOSTデバイス 119
5−10、Infinion 120
5−10−1、MOST光コネクタ 120
5−10−2、欧州でのIDB-1394の動向 121
第6章、カーエレクトロニクス企業の車載LANの取り組み 122
6−1、デンソー 122
6−1−1、車載LAN開発動向 122
6−2、光洋精工 123
6−2−1、アクティブステアリング 123
6−2−2、Steering by Wire 124
6−3、NOK 126
6−3−1、Brake by Wire 126
6−4、日立製作所 127
6−4−1、Brake by Wire 127
6−5、愛三工業 128
6−5−1、Drive by Wire 128
6−6、ケーヒン 129
6−6−1、Drive by Wire 129
6−6−2、FlexRay 129
6−6−3、リアルタイムOS 130
6−7、松下電器産業(松下電子部品) 131
6−7−1、ポジションセンサー 131
6−8、アルプス電気 132
6−8−1、ハプティック制御技術 132
6−9、Hella 133
6−9−1、Drive by Wire 133
|
Address:2-6-30-918 Kameido koto-ku Tokyo Japan 136-0071 TEL 81-3-5627-7045 FAX 81-3-5627-7046 E-mail info@srdj.co.jp |